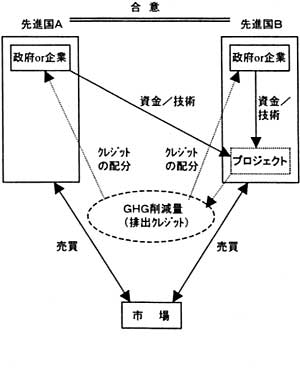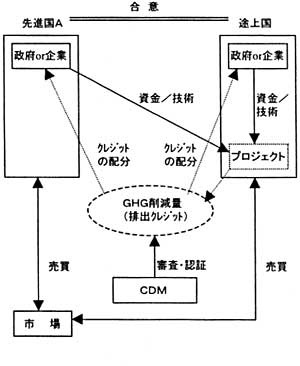|
|
|
|
|
<参考> |
||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
(GHG:温室効果ガス) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
要 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
リ ッ ト |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
念 図 |
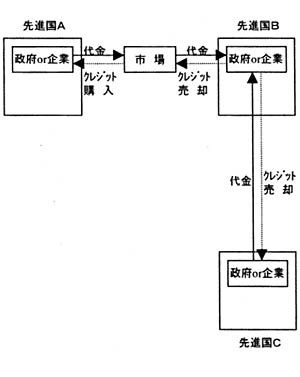 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
<参考> |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
2000年10月13日 |
||
|
|
|
|
|
1.電気事業としての基本的考え方 |
||
|
○ |
地球規模でコスト効果的にCO2等の排出抑制が可能であり、電気事業としても国内対策を補完する手段として重要と考える。 |
|
|
○ |
我が国の進んだ電力技術、ノウハウの海外移転が促進されるというメリットもある。 |
|
|
|
|
|
|
2.京都メカニズムのルール、枠組みについての意見 |
||
|
○ |
地球規模でコスト効果的であるべき。 |
|
|
|
・ |
京都メカニズムの活用の上限を定めるべきでない。 |
|
|
・ |
適正な価格で取り引きされる市場が形成されるべき。そのためにも、幅広く民間を参加させるべき。 |
|
|
・ |
京都メカニズムの運営費用を最小化すべき。 |
|
|
・ |
植林等大気中のCO2吸収源対策について、共同実施に加え、CDMにおいてもプロジェクトの対象とすべき。 |
|
○ |
簡潔でわかりやすく、安心して活用できる仕組みであるべき |
|
|
|
・ |
市場が十分発達するまでは、売り手責任の方が適切。 |
|
○ |
持続可能な仕組みであるべき |
|
|
|
・ |
プロジェクトの継続性、事業性の確保が重要であり、利益を伴う事業活動であっても、CO2等の削減に寄与するものであれば、認めるべき。 |
|
|
・ |
持続可能性の評価としては、受入国の判断が重要であり、原子力等特定の技術をあらかじめ除外すべきではない。 |
|
○ |
実施国、受入国双方に有益な仕組みであるべき |
|
|
○ |
早期の取り組みを認めるとともに推奨すべき |
|
|
|
・ |
「実行しながら学ぶ」という考え方のもと、必要最小限のルール、枠組みを早期に整備すべき。 |
|
|
|
|
|
3.国内制度に関する考え方 |
||
|
○ |
排出量の初期割り当てを伴う方式は、公平性、実効性の観点で種々問題が多く受け入れがたい。 |
|
|
○ |
国が排出量取引等の財源を確保する場合でも、基本的には歳出の見直しにより捻出すべきであり、新規の課税を行うべきでない。 |
|
|
|
|
|
|
以上 |
||
|
|
|
|
|
戻る |
||
|
|
|
|