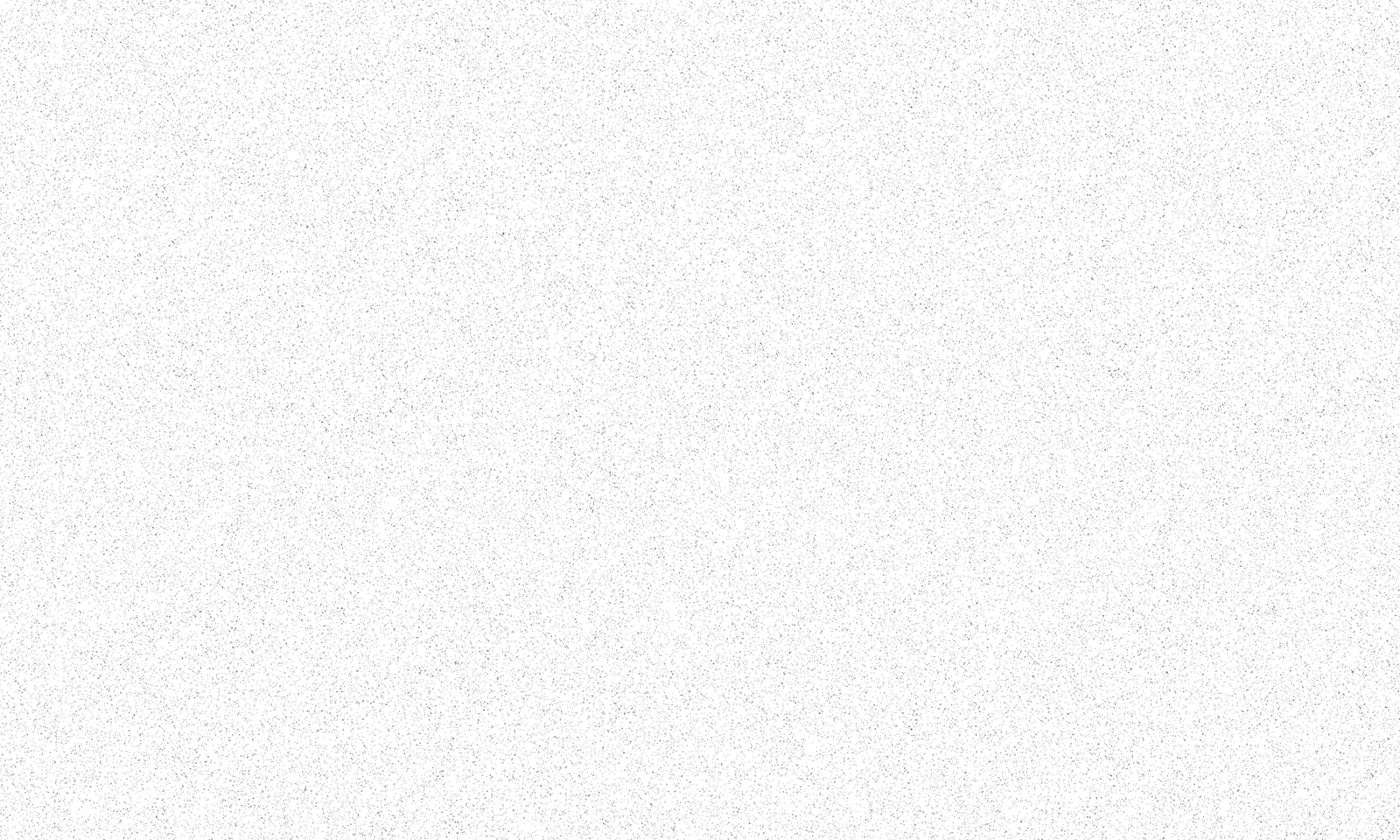History 原子燃料サイクルの歴史
エネルギー資源に乏しい日本がどのようにして原子力発電と原子燃料サイクルを導入・発展させてきたのか、その歴史と背景をご紹介します。
1953 年
国連でアメリカのアイゼンハワー大統領が原子力平和利用宣言
アイゼンハワー米国大統領による『Atoms for Peace』と呼ばれる演説後、世界的に原子力の平和利用が推進され始める
1955 年
原子力基本法の成立
原子力の研究や開発、利用は平和を目的としたものに限ることや、「民主」「自主」「公開」の三原則にもとづくことが定められ、日本における原子力利用が始まる
1956 年
原子燃料公社設立
1956 年
最初の「原子力研究開発利用長期計画」(原子力長計)の策定
・わが国における将来の原子力の研究、開発および利用については、主として原子燃料資源の有効利用の面から見て増殖型動力炉がわが国の国情に最も適合すると考えられるので、その国産に目標を置くものとする
・燃料要素の再処理および廃棄物の分離処理については、その初期には日本原子力研究所(原研)が研究的に実施するが、その後は核燃料物質の散逸を防止し、安全性を確保するため原子燃料公社(後の動燃事業団)において集中的に実施するものとする
1956 年
原子力の平和利用の一環として日米原子力協定を締結
1957 年
日本原子力発電設立
1957 年
原子燃料公社が東海再処理工場の前身である東海精練所を設置
1961 年
第二次原子力長計の策定
・燃料サイクルの円滑な実施をはかるため、わが国においても早期に再処理方式を確立しておく必要がある。このような観点から1960年代後半に完成を目標として原子燃料公社に再処理パイロットプラントを建設し、再処理の工業化試験を実施する
1963 年
東海再処理工場の工事が着工
1967 年
第三次原子力長計の策定
・(東海再処理工場のみでは処理能力が不足することから)新たな再処理工場を建設する必要があり、その際民間企業にて行わせることが期待される
1967 年
動力炉・核燃料開発事業団(動燃)の設立
1972 年
第四次原子力長計の策定
・再処理事業の安定操業のためには、スケールメリットを生かすことが重要なので、電気事業者を含む関係業界が早急に協力体制の確立を進めることが望まれる
1973 年
第一次オイルショック
1978 年
第五次原子力長計の策定
・第二再処理工場(現在の六ヶ所再処理工場)は、本格的な商業施設として、その建設・運転は、電気事業者を中心とする民間が行うもの
・第二再処理工場の運転開始までの措置としては、海外への委託によって対処する
1978 年
第二次オイルショック
1980 年
日本原燃サービス(のちの日本原燃)が設立
1980 年
東海再処理工場のホット試験が終了し、合格証が交付
1984 年
電気事業連合会が青森県と六ヶ所村に、ウラン濃縮、再処理および低レベル放射性廃棄物埋設の3施設を六ヶ所村に立地したい旨を正式に申し入れ
1985 年
日本原燃産業が設立
1985 年
青森県知事および六ヶ所村村長より、電事連に対し正式に立地受諾の回答。立地協定の締結
1988 年
六ヶ所村のウラン濃縮工場が着工
1990 年
六ヶ所村の低レベル放射性廃棄物埋設センタ-が着工
1992 年
日本原燃サ-ビスと日本原燃産業が合併。日本原燃が誕生
1992 年
六ヶ所村でウラン濃縮工場と低レベル放射性廃棄物埋設センターが操業を開始
1993 年
六ヶ所再処理工場の建設が開始
2006 年
六ヶ所再処理工場でアクティブ試験を開始
2011 年
東日本大震災
2013 年
福島第一原子力発電所の事故の教訓や国内外の知見を踏まえた新規制基準が施行
2020 年
六ヶ所再処理工場・MOX燃料工場の事業変更許可を取得
2024 年
六ヶ所再処理工場・MOX燃料工場のしゅん工目標を見直し
日本原燃は、六ヶ所再処理工場については「2026年度中」、また、MOX燃料工場については「2027年度中」とする新たなしゅん工目標を公表