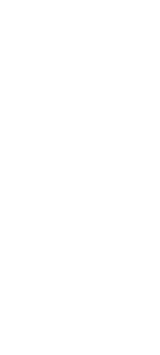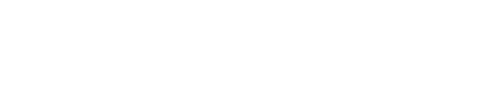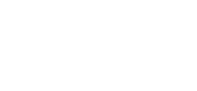
政府は9月14日、今後のエネルギー政策の大きな方向を示す「革新的エネルギー・環境戦略」を決定し、「2030年代に原発稼働ゼロを可能とするよう、あらゆる政策資源を投入する」という方針を示しました。
エネルギー資源に乏しいわが国は、主要国の中でもエネルギー供給構造が極めて脆弱です。その一方で、世界有数のエネルギー消費大国でもあります。エネルギー政策はまさしくわが国を支える基幹政策であり、選択を誤れば国家の将来に大きな禍根を残す可能性もあります。
原子力ゼロを目指す場合、次のような深刻な課題が予想されますが、今回の戦略では、このような課題について国民や産業界が納得できるような解決の道筋が示されていないと考えます。
わが国は2度のオイルショックの経験から、これまで特定のエネルギーに依存せず、多様なエネルギーをバランスよく組み合わせることで、安定したエネルギー基盤の構築に努めてきました。私たちは、エネルギー源の多様性を確保する観点からも原子力発電を引き続き重要な電源として活用していくとともに、ウラン資源を有効に活用する原子燃料サイクルをしっかりと進めていく必要があると考えています。このため、その大前提となる原子力発電の安全確保に全力で取り組み続け、世界最高水準の
安全を追求していく覚悟です。
政府は今後のエネルギー・環境政策について、「関係自治体や国際社会等と責任ある議論を行い、国民の理解を得つつ、柔軟性を持って不断の検証と見直しを行いながら遂行する」(9月19日閣議決定)としています。私たちは、今後、できるだけ早い時期に見直しに向けた議論が行われることを望みます。
わが国のエネルギー自給率はわずか4%程度と極めて低い水準であり、エネルギー資源の多くを輸入に頼っています。その輸入元を見ると、一次エネルギー供給の4割を占める石油が中東に依存しているのに対し、原子力発電の燃料であるウランは政情が安定した国が中心です。原子力発電を放棄することは、安定的に調達できるエネルギー資源を失うことはもとより、化石燃料調達時の価格交渉力低下につながり、低廉で安定したエネルギー資源の確保という観点から大きな問題があります。
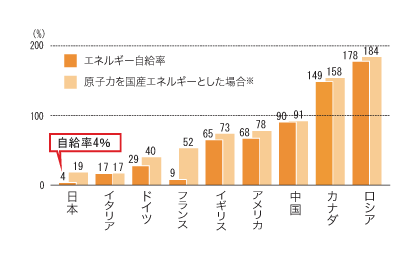
- ※原子力発電の燃料であるウランは、一度輸入すると長期間使用することができ、再処理してリサイクルすることが可能なため準国産エネルギーとして扱われます。
- 出所:ENERGY BALANCES OF OECD COUNTRIES,2012/
ENERGY BALANCES OF NON-OECD COUNTRIES,2012
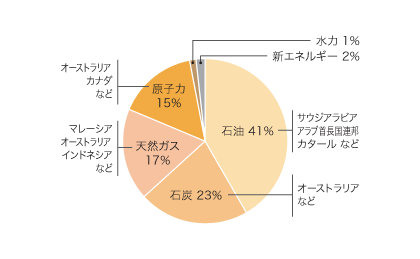
- (注)四捨五入の関係で割合の合計が100%にならないことがあります。
- 出所:ENERGY BALANCES OF OECD COUNTRIES,2012/
ENERGY BALANCES OF NON-OECD COUNTRIES,2012などより作成
現在、電力会社は停止している原子力発電に代わり、火力発電で供給力を確保しています。このため、震災前と比較し天然ガスなどの燃料費が年間約3兆円増加すると試算されており、多額の国富が海外に流出することになります。また、原子力発電をゼロとし、太陽光、風力など高コストの再生可能エネルギーを大量導入する場合、2030年のご家庭の電気料金が最大で2倍に上昇するとの試算もあります。企業活動への影響も大きく、国際競争力の低下や生産拠点の海外移転、雇用環境の悪化につながり、経済を基盤とするわが国の国力が衰退する事態にもなりかねません。
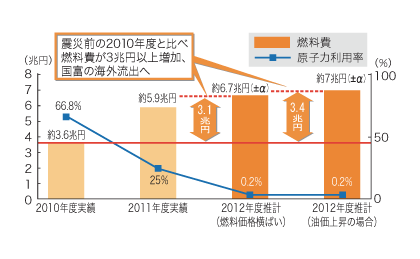
- ※油価及び為替については、2010年度が1バレル=84ドル、86円/ドル、2011年度実績及び横ばいのケースは1バレル=114ドル、79円/ドル。油価上昇ケースでは、2012年3月実績が1バレル=121ドル、81円/ドル(2011年度実績比+9%)と上昇傾向であることを踏まえ、2011年度実績からLNG、石油価格が1割上昇すると仮定。
- 出所:需給検証委員会報告書より作成
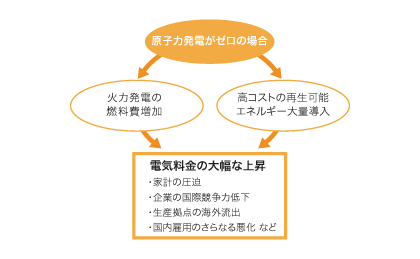
原子力発電は発電時に二酸化炭素(CO2)を排出しないため、地球温暖化防止の観点からも有効です。
しかし、東日本大震災以降、停止した原子力発電に代わり火力発電を増やしたため、節電などにより使用電力量は減少したにもかかわらず、2011年度のCO2排出量は2010年度より大幅に増えています。今後、原子力発電の停止が続けば、わが国の地球温暖化対策に深刻な影響を与えかねません。
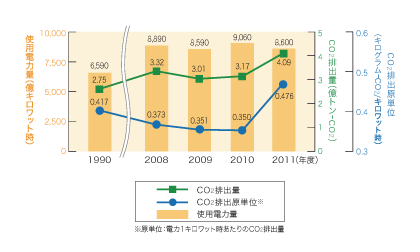
- 2008~2011年度のCO2排出量及びCO2排出原単位は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」で定められた方法により京都メカニズムクレジットなどを反映した数値
- 出所:電気事業連合会・電気事業における環境行動計画より作成
純国産エネルギーで枯渇の心配がなく、CO2の発生など環境負荷の少ない再生可能エネルギーは、重要なエネルギーとして着実に進める必要があります。しかし、エネルギー密度が低く、太陽光や風力の大量導入には広大な面積が必要です。政府が6月に示した試算では、原子力発電をゼロとした場合、太陽光発電は一戸建て住宅の1200万戸に導入し、風力発電は東京都の2.2倍の用地が必要としています。また、天候次第で出力が変動するうえ、風力には適地が北海道や東北に偏在しているという課題もあります。そのため、発電量の増減を吸収するバックアップ電源や蓄電池の整備、送電網の増強など多額の対策費用もかかります。大量導入にあたっては、その実現性を十分に検証する必要があります。
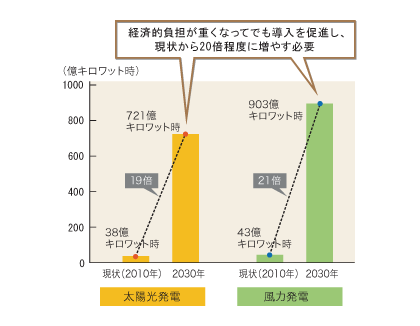
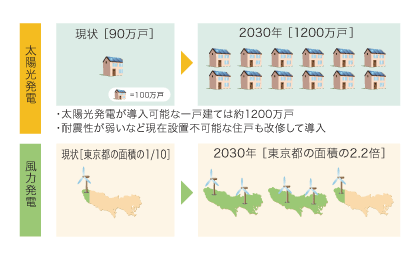
- 出所:エネルギー・環境会議資料より作成
原子力は高度な知識と技術を必要とする専門的な分野ですが、それを支えるのは人の力です。原子力発電所の安全性向上の取り組みには終わりはなく、人材を確保・育成し、技術を継承していくことが不可欠です。原子力ゼロを目指すことになると、こうした人材基盤が弱くなり、原子力の安全管理に支障をきたす恐れがあります。
わが国は、米国をはじめ多くの国と原子力協定を締結し、密接な協力関係のもと原子力の平和的利用を進め、国際的な核不拡散体制の強化に貢献してきました。これまで培ってきた技術は原子力発電の導入を計画している新興国からも期待されています。
原子力ゼロを目指すということは、こうした各国との協力関係や、わが国の経済成長戦略の柱でもある原子力輸出など、国際関係にも大きな影響を及ぼしかねません。また、わが国は非核保有国の中で唯一、使用済燃料を再利用する権利を認められていますが、一度放棄すると二度と得られない可能性があります。
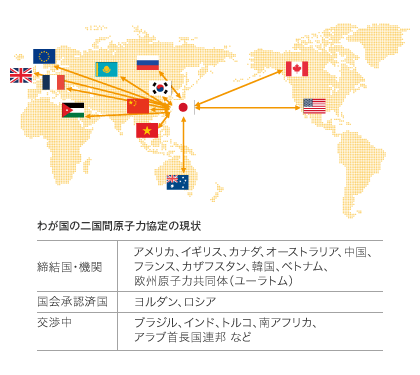
- ※二国間原子力協定:核物質・原子力資機材等の移転先国における平和的利用や核不拡散等を確保するための法的な枠組み。
- 出所:基本問題委員会資料より作成
原子力発電所の立地自治体には、長年にわたり原子力政策にご理解とご協力をいただいてきました。
原子力発電ゼロを目指すことになれば、立地地域の皆さまの思いをないがしろにし、その信頼を失いかねません。また、そのようなことになると今後、原子力発電所を継続して運営していくことが困難になる可能性があります。