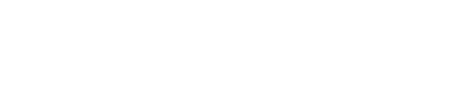作家
曽野 綾子氏
1931年東京生まれ。聖心女子大学卒業。「遼来の客たち」が芥川賞候補となり文壇にデビュー。著書に「無名碑」「神の汚れた手」「天井の青」「人間の基本」など。1979年ローマ法王庁よりヴァチカン有功十字勲章、93年恩賜賞・日本芸術院賞、97年海外邦人宣教者活動援助後援会代表として吉川英治文化賞、読売国際協力賞を受賞。03年文化功労者となる。
この雑誌では当然のことだが、多くの専門家たちが東日本大震災による原発の事故に触れておられる。しかし私にはそれができない。私は自然科学系の発想にきわめて弱い頭しか持っていないので、小説家として生きて来た。現代の日本では、どんな人間も生きることは許されるが、素人が専門家の領域に入って発言することは越権だと私はかねがね思って来たのだ。私は原発継続の可否を、優秀な同胞の決断に任せて沈黙することにした。その代わり彼らが、すべての結果の責任を負うことになるだろう。しかし委ねることのできる多くの同胞を持つ私は幸せなのである。
私は人生の後半になって、アフリカなどの途上国を百二十五カ国も歩くことになった。私は満月の夜のサハラの中心部で眠り、カメルーンの奥地では、ホタルの光を波のようにかき分けて入る原生林の奥のピグミーの村を訪ねた。それらの広大な地域の特徴は、すべて電気がないということだった。
かつてソニーの盛田昭夫氏が、「ソニーにとっては存在しないのも同然の土地」と明晰に言われた広大なアフリカの大地である。当然だろう。電気のない地域では電気器具が売れないのだから、ソニーは一店の支店をおく必要もなかったのだ。
そうした場所には際立った文化的特徴があった。たとえ人の住む村があったとしても、電気のない土地には、民主主義は全く存在しない。その気配さえないのである。そうした原始の地域は、今でも族長支配の社会形態の元にあり人々は昔ながらの仕組みで暮らしている。電気と民主主義とは、完全に不可分の関係にあるということを日本人は知らない。
たとえ村に学校があったとしても、午後になって子供たちは家に帰ると、臼に米を入れて何時間もかかって杵で搗く。兄弟姉妹が代わり合ってその作業をするが、それが終わって日が沈む頃、人々は家の前の竈に火を起こして米を炊きおかずを煮る。貴重な薪の香ばしい煙が村の道にたなびき、やがて竈の火が夕暮の村に赤々と浮き立つ。
人々は太古からそうして暮らして来た。近年、総選挙が初めて行われた国もあるが、人々は族長の命じる党に一票入れて来ただけだ。多くの人は字が書けないから、絵や色で投票する。電気のない土地はその土地なりの眠たげな平穏に包まれているが、それは私たちが目指すような個性の尊重される社会ではない。個人を生かしているのは電気の力だけなのである。