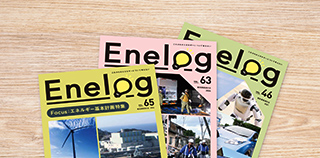よくあるご質問
皆さまからよく頂戴するご質問とその回答を掲載しております
当会・このサイトについて
-
個人情報の提供が不安です。
電気事業連合会では、個人情報保護の重要性を十分に認識し、本会の個人情報保護方針に遵守した運用を行っております。また、本サイトから個人情報を取得する場合には、128bit暗号化通信により保護された環境にて取得しています。
-
サイトが正しく表示できません。
本サイトを快適にごらんいただくためには、当会が基準としている環境でのご利用を推奨しております。また、プラグインを必要とするコンテンツも含まれていますので、詳しくは「このサイトについて」ページにて推奨環境をご確認ください。
-
電気事業連合会のサイトへリンクを貼りたいのですが、申請など必要ですか?
本サイトへリンクする際のご連絡は不要です。リンクに際しては、「リンクについて」の注意事項を遵守いただきますようお願い申しあげます。
-
このサイトの情報やデータを二次利用してもいいですか?
WWW.FEPC.OR.JP(以下、本サイト)に掲載されている文章、図版、写真、動画、音声その他には著作権があり、日本国内法並びに国際法(ベルヌ条約並びに万国著作権法)において保護されています。
電気事業連合会に著作権(帰属したものを含む)がある著作物は、無断で印刷物、Webサイト、放送、その他著作物に利用することはできません。
くわしくは本サイト「著作権について」のページを参照ください。 -
電気事業連合会とはどういう組織ですか?
電気事業連合会は、日本の電気事業を円滑に運営していくことを目的として、1952年(昭和27年)に全国9つの電力会社によって設立されました。以来、地域を代表する電力会社間の緊密な対話と交流をはじめ、新しい時代の電気事業をつくり出していくための創造的な意見交換の場として貢献してきました。また、日本のエネルギー産業の一翼を担うという自覚のもと、安定したエネルギー供給体制の確立に向けても多彩な活動を行っています。2000年(平成12年)3月に沖縄電力が加盟し、現在10電力体制で運営されています。
放射線の影響
-
【15】原子力災害時に、ヨウ素剤が配布されると聞いたが、いつどのように飲むのか、どのような効果があるのか?
放射性ヨウ素の摂取が予測される直前又は数時間前から直後までにヨウ素剤(ヨウ化カリウム)を服用し、あらかじめ甲状腺にヨウ素を蓄積させておくことで、放射性ヨウ素を吸収・摂取してもそのほとんどが甲状腺に到達することなく排出され、甲状腺の内部被ばくを低減します。
-
【14】危険な放射線下作業はすべて協力会社にやらせているのではないか?
発電所の運転・保守には、多くの種類の作業があり、それぞれに役割を分担した多くの人が働いております。
例えば、一つの作業をとっても、直接に作業する人、作業を計画する人など、作業の内容によって役割が異なります。これは、それぞれの作業に応じた知識と技能を持った専門の人々が効率よく行うことが望ましいからです。
したがって、放射線を多く受ける作業だからといって、協力会社の社員に行わせているものではありません。
発電所内での作業は、放射線や放射性物質が比較的多い場所での作業もありますが、作業の実施に当たっては、一般の作業安全に加え放射線管理に万全を期して、できる限り放射線を受けないようにすると同時に不必要な放射線を受けないようにしています。
また、協力会社の社員についても、電力会社社員と同様、きちんと放射線管理を行っています。 -
【13】広島、長崎の原爆被爆者の疫学調査は行われたのか?調査結果はどうか?
1945年に広島、長崎に投下された原爆によって被爆した方々に関する疫学調査は、LSS(寿命調査:Life Span Study)と呼ばれ、1950年から開始され調査対象者は10万人を超えています。
この調査の結果によると、500ミリシーベルトよりも高い線量を受けた被ばく者には放射線によるがんの発生増加が認められますが、100ミリシーベルトよりも低い線量を受けた被ばく者には有意な増加は認められていません。また、放射線による遺伝的影響の発生は確認されていません。 -
【12】原子力発電所の放射能による放射線は自然放射線やX線より危険なのではないか?
自然放射線と人工放射線の区別は、放射線の源が自然のものか人工的なものかによるのであって、放射線の性質に違いがあるわけではありません。
-
【11】微量の放射線でも健康に影響があると主張する研究者グループが欧州にいるが、彼らの主張の妥当性は?
国際機関(ICRP:国際放射線防護委員会)の勧告(および国内法令)で採用されている線量限度について、この研究グループ(欧州放射線リスク委員会のことと思われますが)は大幅に低くする必要があると指摘しています。我が国の専門機関(原子力委員会専門部会)および海外においては、ICRP勧告が、国連科学委員会で認められた科学的知見に基づき、放射線防護上十分保守的な値を採用しているため、このグループの指摘を妥当ではないとしています。
-
【10-2】食品向けに放射線が照射されていると聞くが、その照射された食品は安全か?
1980年に国連食料農業機関(FAO)・国際原子力機関(IAEA)・世界保健機構(WHO)の3機関合同の専門委員会で、10kGy以下の線量では食品全般に対して問題がない、という安全宣言を出しており、40カ国以上の国で食品照射が許可されています。日本で照射が認められている食品はじゃがいもで、照射することで、発芽を遅らせ保存期間を長くしています。
-
【10-1】生活環境や産業で,放射線(放射性物質)はどのように利用されているのか?
人工放射線は医療・工場・農業などさまざまな場面で利用され、わたしたちの生活にとても役立っています。
(1)医療では、病院でのX線検査や各種病気の診断、ガン治療として利用しております。
(2)工業では、半導体加工や厚みの測定・化学分析・各種測定、非破壊検査、溶接検査等に利用しております。
(3)農業では、品種改良や化学薬剤を使わないで害虫駆除、食品を保存するのに利用しております。 -
【10】なぜ世の中から放射線は無くならないのか?
地球誕生の時から地球上に放射線は存在しており、また宇宙からも常に放射線は降り注いでいます。放射線は上手に使えばデメリット以上のメリットがあります。
-
【9-3】原子力発電所周辺の放射線測定はどのように行っているのか?
原子力発電所から運転に伴って放出される放射性物質が周辺の環境に影響を及ぼしていないことを監視するため、環境放射線モニタリングが行われています。環境放射線モニタリングは、空間の放射線量を測定したり、空気・水・野菜や魚などの放射能を測定しています。測定頻度は、連続または定期的に、地方自治体及び電力会社などにて実施され、両者の測定結果をチェックし、技術的に検討、評価され公表されています。
-
【9-2】自分の周りの放射線量を知りたい、測定してほしいのだが?
文部科学省より東日本を中心とした放射線測定結果が公表されています。
文部科学省 放射線モニタリング情報 -
【9-1】放射線と物質の相互作用とは?
電離作用と蛍光作用、透過作用があります。
電離作用は原子中の電子をはじき飛ばす働きです。類似の作用として電子を外側の軌道に遷移させることを励起作用と言います。
蛍光作用は放射線が物質に当たる際に光を発する働きです。
透過作用は物質を通り抜けることをいいます。
これらの電離作用や、蛍光作用を利用して放射線測定器は作られています。 -
【9】五感で感じない放射線はどのようにして測るのか?
放射線と物質の相互作用を利用して測定します。
-
【8-1】放射線は微量でも害があるのではないか?
放射線防護を検討する国際的な組織「国際放射線防護委員会(ICRP)」では放射線防護・安全の立場から、どんなに少ない放射線でも放射線を受けると影響を生じる可能性があるという非常に慎重な仮定で検討されています。
しかし、放射線を受けた量に応じて影響の割合が増加する可能性があるという意味で、実際上影響を考える必要がある放射線の量は、広島・長崎の原爆被爆生存者調査などからはっきりとわかっているように、数百mSvという大きな線量の場合であって、100mSvよりも低い線量を受けた被ばく者には、がんなどの発生について有意な増加は認められていません。
したがって、私たちが自然から受けている放射線やICRPが勧告している線量当量限度の放射線の量では、人の健康に影響が認められないようなレベルと考えられています。 -
【8】ただちに影響がないということは、将来影響があるということか?
広島・長崎の調査から、これまでに遺伝的影響はみられていません。
-
【7】放射線について“分からないこと”は、なぜ分からないのか?
100mSv未満での被ばくでがんが増えることを示すだけのデータが存在していないことです。他の要因(運動不足、飲酒など)と区別できるだけの有為な差がありません。
-
【6-1】原子力発電所の放射線管理下で働く作業者の放射線管理は,どのように行っているのか?
原子力発電所で働く作業員を放射線から防護するために,作業員一人ひとりの放射線量について測定・評価を行い,法令に定める線量限度を超えないように管理しています。
(1年間で50mSv、5年間で100mSv)また,測定値は個人に通知されるとともに,放射線従事者中央登録センターに登録され,どこの原子力発電所で働いても,その人が過去に受けた放射線量がすべて分かるようになっています。 -
【6】なぜ一般公衆は年間1mSv、放射線業務従事者は年間50mSvなのか?
管理されているかいないかの違いです。
-
【5】震災後の放射線の影響(雨、風、雪)はどうだったのか?
これまでも雨・雪が降ると空気中のRnが降下し、地面近傍の放射線が上昇していました。福島第一原子力発電所からの放射性物質は日本、世界中に広がりましたが、現時点では直ちに人体に影響を与えるレベルではありません。
-
【4-2】原子力発電所から外部へはどれくらい放射線が放出されているのか?
原子力発電所から放出される放射性物質の量は、それにより周辺の人々が受ける放射線量について、原子力安全委員会が定めた年間0.05mSv以下という目標値を超えないように厳正に管理されています。なお、実際の放射線量は、この目標値を大幅に下回っています。
-
【4-1】東日本で(Csが検出された場所で)栽培された野菜を食べて問題はないのか?
出荷制限または摂取制限の行われていない地域であれば、問題有りません。出荷制限または摂取制限の行われている地域は厚生労働省のホームページより確認できます。
-
【4】放射線・放射能はどこへ行くのか?
放射線はいろいろな物にエネルギーを与えてなくなります。放射能は、食物連鎖等によって移動します。放射能自体は、時間が経過して放射線の放出に伴い減少していきます。放射能が半分になる時間を半減期と呼んでいます。また放射能は代謝により排泄されて、減少していきます。代謝により放射能が半分になる時間を特に生物学的半減期と呼びます。
-
【3-2】どれくらい被ばくするとガンになるのか?
放射線の影響は染色体内のDNAに損傷を与え、異常な細胞(がん細胞)が生まれ発がんすることがあり、一度に(まとめて)100~150mSvを超えると発がん率が上昇することがわかっています。これは確率的影響と呼ばれています。
がんは放射線以外に、化学物質やウィルス、紫外線で発生することが認められており、国立がん研究センターより、生活習慣と放射線によって発がんする相対リスクが報告されています。例えば野菜不足によるリスクは150~200mSvの被ばくによるリスクに相当します。また喫煙や毎日3合以上の飲酒は2,000mSvの被ばくに相当します。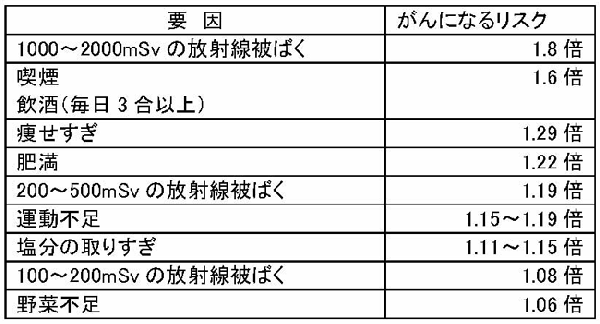
-
【3-1】放射線による人体への影響はどのようなものか?影響は蓄積されるのか?
放射線の影響はDNAに損傷を与え、(1)異常な細胞(がん細胞)が生まれ発がんすることと、(2)細胞が死ぬことです。
(1)は一度に(まとめて)100~150mSvを超えると発がん率が上昇することがわかっています。(2)は一度に250mSvを超える大量な被ばくで白血球の減少や脱毛などの現象として認められます。つまり100mSv未満では、放射線による影響(発がんリスク増加)は確認されていません。
ゆっくりと(少しずつ)放射線被ばくした場合は、一度に(短時間に)被ばくした場合と比べ影響が小さくなります。これは生物にはDNAが損傷しても修復する能力が備わっているためです。まれにDNAの損傷が修復されない場合でも、この傷をもった不良細胞は自爆して人体組織から排除されます。また、放射性物質を体内に取り込んだ場合でも、体の代謝作用により排泄されるので、いつまでも溜まっているということはありません。
これまでの疫学的調査からは、放射線による子や孫への遺伝的な障害は確認されていません。 -
【3】放射線を受けるとどのような人体影響が出るのか?
細胞のDNAを損傷させる結果、がんになったり、白血球が減少したりします。しかし人間にはDNAの損傷を回復させる能力があります。
-
【2-4】自然界の放射線と人工の放射線では身体への影響が異なるのではないか?
放射線を発する物質は自然界に元来から存在するもの(40K、222Rnなど)と、人為的に発生するもの(例えば原子炉内で生成)があります。
・人工放射性物質から出る放射線も自然放射性物質から出る放射線もアルファ線、ベータ線、ガンマ線という種類は同じです。
・人工放射能から発する放射線のエネルギーと自然放射能から発生する放射線エネルギーは異なりますが、このエネルギーによる人体への影響をシーベルト(Sv)という統一した影響の指標に換算しています。つまり、シーベルトという単位で比べれば、自然放射能も人工放射能も同じ土俵で評価出来ます。
・自然界(宇宙、大気、食物、地面等)からは、平均年間2.1mSv被ばくしています。うち、40K(半減期12.8億年)は食物を経由して体内に取り込んでおり、年0.18mSv程度に相当します。 -
【2-3】放射性物質の違いによる人体への影響はあるのか?
放射性物質が違うと、放出される放射線の種類、そのエネルギーが異なります。放射性物質の種類によって集積しやすい臓器も異なります。その影響を評価するために、人体への影響をシーベルト(Sv)という単位で統一された指標に換算しています。
-
【2-2】外部被ばくより内部被ばくの方が影響が大きいのではないか?
同じ放射性物質の量(ベクレル、Bq)であれば、体の外にあるときと内部にあるときで影響が違います。外部被ばくではガンマ線だけの影響ですが、内部被ばくの場合は、ガンマ線に加えて飛ぶ力の弱いアルファ線やベータ線の影響を受ける場合があるので、それらの影響も考える必要があります。
また、放射性物質の種類によって、集積しやすい臓器がある場合は、その臓器への影響を個別に考慮する必要があります。これらのことを含めて人体への影響の評価のために考えられたものが実効線量(単位はシーベルト、Sv)です。
体内の放射性物質から受ける内部被ばくの実効線量は、摂取した放射性物質の量(Bq)に実効線量計数(Sv/Bq)を掛けることにより求められます。このようにして得られた実効線量を用いれば、内部被ばくの影響と外部被ばくの影響を同等に扱うことができます。同じ実効線量であれば内部被ばくでも外部被ばくでも影響の大きさは同じです。 -
【2-1】同じ線量でも子供への影響は大きいのではないか?
成人に比べれば幼若で成長過程にある小児のほうが分裂している細胞が多いため、放射線に対する感受性が高くなります。これまで流通している食品中の放射性ヨウ素や放射性セシウムによる内部被ばくは、胎児や子どもでも、事故直後の1年間に0.1mSv程度以下であると見積もられています(2011年7月12日の厚生労働省の試算)。この程度の線量であれば、健康への影響を心配する必要はありません。ただ不要な被ばくは可能な限り低く抑えることが望ましいです。
-
【2】放射線は人体にどのような作用をするのか?
人間の細胞の中の遺伝子(DNA)に作用し、損傷を与えます。損傷の程度により、異常細胞(がん細胞)を生成したり、細胞そのものを殺すことがあります。
-
【1-2】ベクレルとシーベルトの換算について
ベクレルは放射性物質が放射線を出す能力を表します。一方シーベルトは人体が放射線で受けた影響を示す単位です。同じベクレル数であっても、放射性物質ごとに放出されるエネルギーが異なること、体内での挙動が異なることから、人体に与える影響(シーベルト)が異なります。放射性物質の種類やどこから取り込むかで影響が異なるため、個別に換算係数が異なります。
-
【1-1】私たちの身の回りにも放射線はあるのか?
私たちの身の回りには、各種の放射線があります。地球には絶え間なく宇宙からの放射線(宇宙線)がふりそそぎ、また、地球上の大気や、岩石・土の鉱物に含まれる放射性物質からも放射線が放出されています。さらに食品や水にも放射性物質が含まれており、放射線が出ています。こうした放射線を自然放射線と呼び、日本では、年間平均約2.1mSv(世界では約2.4mSv)を受けています。
40K(半減期12.5億年)は食物(ほうれん草、海草類など)を経由して成人で約4,000Bq体内に取り込んでおり、年0.2mSv程度に相当しています。。
また医療で用いるX線の場合、胸部レントゲン撮影1回当たり約0.05mSvを受けています。
宇宙線は高度が高いほど強く、例えば東京とニューヨークを飛行機で移動すると、0.1mSv地上にいる間よりも多く被ばくすることになります。 -
【1】放射線はどのようなものか?また、なぜ放射線があるのか?
不安定な原子核が、より安定な原子核になる時に余分なエネルギーを放出します。このエネルギーが放射線です。このような原子核はある割合で自然界にも存在しています。