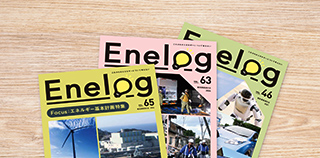【定例会見】今夏の需給の振り返りと今冬以降の需給/原子力の安全性向上に向けた取り組み
今夏の需給の振り返りと今冬以降の需給
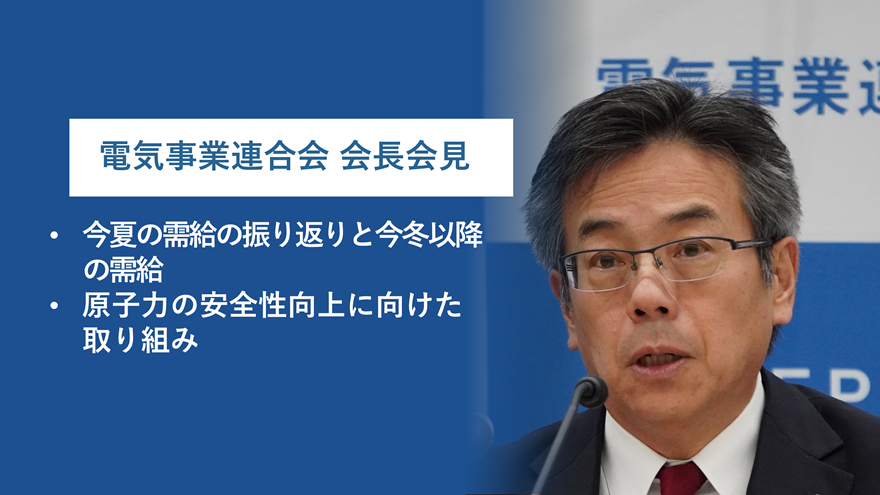
電気事業連合会の林です。本日もよろしくお願いいたします。 さて、本日のテーマは2点にあります。 1点目は、今夏の需給の振り返りと、今冬以降の需給について、申し上げます。 2点目としては、原子力の安全性向上に向けた取り組みについて、お話させていただきます。
まずは、1点目、今夏の需給の振り返りと、この冬以降の需給バランスについてです。 先月の次世代電力・ガス基盤構築小委員会において、2025年度の夏の需給の振り返りと冬の需給対策が示されました。
今年は、ご存知のとおり、夏本番を迎える前の6月の後半から、全国的に異常気象ともいえる大変な猛暑でありました。その中でも、各電力会社は、供給力の確保や設備保全、燃料確保等にしっかりと取り組ませていただきました。
夏場に需要が増加した際には、追加の供給力対策として、揚水発電機の運用切替や余力活用電源を追加で起動する等の対応を行い、安定供給に万全を期したところです。それでも需給が厳しい状況では、需給状況を改善するため、発電事業者の点検等を目的とした電源停止計画の実施時期の調整、延期なども行われました。各関係者の安定供給維持に向けた取り組みに敬意を表したいと思います。
次に、この冬の電力需給についてですが、現時点の見通しでは、安定供給に最低限必要な予備率3%は確保される見通しとなっております。しかしながら、東日本を中心に、一部エリアにおいては、1月、2月の予備率が4%台となっております。非常に厳しい状況です。
天候や気象の変動により需要が想定よりも増加するケースや、電力設備の計画外停止による供給力の減少リスク等も踏まえると、非常に予断を許さない厳しい状況になると考えております。
事業者としては、引き続き、緊張感をもって適切な設備保全や燃料確保に努めてまいりたいと思います。また、需要面となりますが、ディマンドレスポンス、いわゆるDRの普及拡大やエネルギーの効率的な使用の呼びかけも積極的に行うなど、需給両面の対策を最大限取り組んでいきたいと思います。
なお、この冬も節電要請は実施されない見通しですが、電気をお使いのお客さまには、無理のない範囲で、効率的なエネルギー、電気の使用をお願いいたします。
また、次に、先月の小委員会では2026年度の需給見通しについても示されました。今回の数値は速報値であり確定したものではありませんが、今後の電源の稼働状況等により変動する可能性はあります。けれども、夏場の需要の高いときに想定よりも高気温になった場合、東京エリアで予備率が1%を切るという、非常に厳しい見通しが示されました。
その原因として、2026年度は、発電所の長期にわたる補修停止や休止等が重なることが予想されています。また、長期脱炭素電源オークション等を活用した新たな電源は2029年以降順次稼働する予定であるため、2026年度の夏等については、言わばはざまの時期となっております。
需要および供給力については、まだ不確定な部分が多いため、今後、電力広域的運営推進機関において、それらの精査が行われるものと認識しております。また、国においても追加供給力の調達を行う方針が出ております。厳しい事業環境ではありますが、我々事業者としても、できる限り、供給面、需要面の対策を強化してまいります。
一方で、2026年度以降も設備の老朽化を背景に、将来的な脱炭素化を見据えたリプレースに伴う長期休止や、非効率な石炭火力を中心に電源廃止に向けた検討が進められており、中期的にも、供給力が非常に厳しい状況がむしろ増加するのではないかと考えております。
現在、必要な供給力を効率的に確保するための制度として、容量市場があります。今年度実施している容量市場の包括的検証を通じて、将来、需要の伸びが想定される中で、適切な供給力を容量市場によって確保できるかといった課題について、一つ一つ丁寧に確認していく必要があります。その上で、至近の需給状況も踏まえ、必要な見直しをスピード感をもって実施していくことが重要と考えております。
加えて、国や電力広域的運営推進機関においては、持続的な供給力の確保に向けて、容量市場といった既存の仕組み以外でも、新たな仕組みについて検討されています。長期脱炭素電源オークションの活用やGX-ETSの導入等、脱炭素化の取り組みを進める一方で、長期にわたっても、電力の安定供給を維持できる基盤構築が必要です。様々な政策やニーズはありますが、各政策の優先順位をつけて、スピード感や柔軟性をもって検討が進められることが望まれると私は考えております。
原子力の安全性向上に向けた取り組み
続きまして、中長期的な供給力確保に向けた原子力の最大限の活用に向けた取り組みについて、申し上げます。
事業者としましては、安全確保の取り組みと、もちろん地元のご理解を大前提に、原子力の再稼働や稼働率向上、さらには長期運転に向けた設備保守等に、それぞれの事業者において最大限取り組んでいるところです。
また、稼働率の向上に向けては、実態に即した規制の予見性向上も重要であり、規制当局との意見交換も進めております。
その一例として、先月の原子力規制委員会と主要原子力事業者との意見交換会において、テロ・重大事故等対処設備、いわゆる特重施設についてATENAが現状を説明しております。
具体的に言いますと、建設業界の労働環境の変化を見据えて、本体施設の工事計画認可から5年以内という現行の経過措置期間を3年間延長して8年としてはどうかと要望したところです。
特重施設は、原子力発電所への航空機衝突等のテロリズムへの対策として設置するものであり、原子力発電所の設備自体の安全性に関係するものではありません。原子力発電所の安全対策は、本体設備の設計やシビアアクシデント対策で達成することができるため、特重施設は、更なるバックアップ対策として捉えていただいてよいかと思います。
従って特重施設が設置されていないプラントも、運転を継続するために必要な安全性は確保されていると考えております。
また、特重施設の工事は、原子力規制委員会の審査を通じて安全性の向上を図っており、大規模になっておりますが、各事業者は早期完成に向けて、それぞれ最大限の努力を継続しております。
一方、建設業においては、労働基準法改正に伴い、2024年4月から、時間外労働の上限規定が適用されました。このような環境変化による人手不足といった他律的な要因により、工事が長期化する懸念される状況であります。
こういった状況変化を踏まえて、今回、ATENAが特重施設設置の経過措置期間の延長について要望しております。原子力規制委員会からは、概要は承知したものの、より詳細に説明するよう求められました。
これに対しては、ATENAを中心に、我々原子力事業者や建設業界等で、実態を説明してまいりたいと考えております。その上で、原子力規制委員会において、実態に応じた見直しがなされるよう要望してまいりたいと考えております。
以上となります。