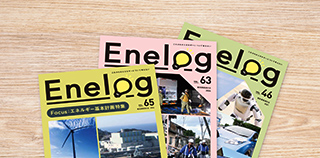【定例会見】原子力の安全性向上の取り組みとサプライチェーン確保に向けた取り組み
原子力の安全性向上の取り組みとサプライチェーン確保に向けた取り組み

本日は、原子力の安全性向上の取り組みとサプライチェーン確保に向けた取り組みについて、お話ししたいと思います。
今週3月11日、福島第一原子力発電所の事故から丸14年を迎えました。今もなお、多くの皆さまに多大なるご迷惑とご負担をおかけしております。原子力事業に携わる者として、大変申し訳なく、思っております。
電力各社は、あのような事故を二度と起こさないという強い決意のもと、原子力発電が有する特性とリスクを常に認識し、行動してまいりました。新規制基準への適合を目指すのはもちろんのこと、それにとどまることなく、自主的な安全性向上に知恵を絞ってまいりました。
例えば、そうした取り組みの一つの例として、事業者のみならず、産業界全体で知恵を結集する仕組みとして、3つの組織を立ち上げ、活動してきました。具体的には、
- まず1つ目は、技術課題の解決や、規制当局との対話を担う原子力エネルギー協議会ATENAです。
- 2つ目は、ピアレビューによる第三者視点からの評価・支援を行う原子力安全推進協会JANSIです。
- 3つ目は、確率論的リスク評価手法の開発に取り組む電力中央研究所・原子力リスク研究センターNRRCです。
こうした組織と事業者が一体となって、安全性の向上に取り組んできました。
本日午前中に、我々事業者と、これら組織のトップが一堂に会し、安全性向上について、議論を行いましたので、簡単にご報告いたします。
議論の場では、それぞれの立場から、常にリスクを意識した発電所の改善や、新たな施策等を通じて、相互連携の重要性を確認しました。原子力を最大限活用していくことの意義を共有した上で、各団体の役割や取り組みを確認しあうことで、大変、有意義な場となりました。
お手元に資料1として、電事連から、説明した資料を配布しております。資料の3、4ページにあるとおり、電力各社の原子力トップによる、安全マネジメント改革タスクチームの活動等を電事連から報告しました。
この活動では、各社の運用面での改善事例や、ベストプラクティスを共有しております。そして、安全性の向上の取り組みが、一過性なものとならないよう、努めております。また、核物質防護、防災対策等についても、他社のベンチマークを行い、自社の弱み等を抽出して、レベルアップを図るようつなげております。
さらには、5ページのとおり、昨年7月に公表した能登半島地震の影響に関する検証結果を踏まえて、有効な水平展開を実施し、対策を進めていることについても、紹介させていただきました。
その上で、本日の議論を踏まえまして、関係者の共通認識として、ステートメントをとりまとめております。資料2として、お配りしておりますので、ご覧ください。
このステートメントにも記載しましたように、我が国のエネルギー安定供給確保と経済成長、また、脱炭素の同時達成に向け、産業界全体が緊密に連携し、自主的かつ継続的に原子力の安全性の向上に、取り組んでまいります。
資源の少ない我が国において、国民生活と経済成長を支え、脱炭素化も同時達成していくためには、原子力の果たす役割は、ますます高まっております。
この原子力回帰の動きは、海外においても、加速しております。例えば、アメリカでは、ご存知のとおりデータセンターへの電力供給として、原子力を活用する動きが出てまいりました。
イギリスやフランスにおいては、エネルギー政策の中で、国としての原子力の開発目標量を明確に定め、実現に向けた事業環境整備が進められております。
また、イタリアやオーストラリアなど、これまで原子力から距離を置いていた国においても、改めて、原子力活用に向けた議論が行われております。先日、選挙が行われたドイツでも、政権交代が起こる中、エネルギー政策の見直しの議論も、出ていると聞いております。
さらに、中国や東南アジアでも、電力需要の伸びを賄うために、新規建設に向けた動きも活発化しているという状況にあると聞いております。
このように、原子力活用の流れが進む中、日本では、事故の教訓を踏まえ、これまでに培ってきた、安全性の取り組みを、不断に進めることが重要です。そして、そうした取り組みを下支えする人材、技術の継承も含めて、サプライチェーン全体を再構築していくことが必要だと考えております。
先日、3月10日に開催されたエネ庁主催のシンポジウムで、電事連から、サプライチェーン確保に向けた課題と対応について、説明させていただきました。お手元の資料3は、そのときの資料となります。
1970年代以降に設置された原子力発電所では、設備の国産化率が90%以上を占めておりました。そのため、国内の最新の技術が集積され、原子力のサプライチェーンにおける強みを発揮しておりました。
一方、東日本大震災以降、日本では、原子力の長期停止により、資料5ページから9ページに記載のとおり、関係する企業の撤退・解散等による技術やノウハウの散逸が発生しています。これにより、優秀な技能職の確保や、人材育成・技術伝承への懸念が顕在化するなど、様々な課題に直面しております。
こうした状況を何とか打破し、業界一丸となって、サプライチェーンを再構築していくことが望まれます。その意味では、第7次エネ基で、原子力の最大限の活用の方針が明記され、その重要性と開発・建設の方針が示されたことは、大変意義があると考えております。
今後も、原子力を持続的に活用するために、サプライチェーンの維持・確保は非常に重要な課題であります。国、メーカー、そして事業者が連携して、これらの課題に真摯に向き合い、対策に取り組む必要があると思います。
サプライチェーンの維持には、事業予見性の向上はもとより、技術・人材を維持する観点から、国が具体的な開発・建設目標量を掲げることが重要だと考えております。その点については、今回のエネ基には反映されませんでしたが、将来にわたり持続的に原子力を活用していくには、いずれ新増設も必要になると考えております。喫緊の課題として、引き続き、国に求めてまいります。
国民生活と経済成長を支えるためには、将来にわたって、原子力発電を含め、全ての電源をバランスよく活用していくことが不可欠です。我々、原子力事業者は、原子燃料サイクルの確立も含めて、常に安全性の向上を追求し、高みを目指してまいります。
本日、私からは以上です。