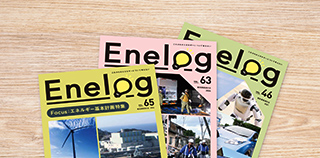【定例会見】大阪・関西万博の開幕/エコキュート出荷台数1,000万台突破
大阪・関西万博の開幕
本日は、大阪・関西万博の開幕、それとエコキュート出荷台数1,000万台の突破の2点について、申し上げます。それに先立ちまして、昨日、開催されました第8回の使用済燃料対策協議会について、一言だけご報告申し上げます。
メディアの皆さまも、現地で取材されていた方も多いと思います。冒頭、原子力事業者として、第7次エネルギー基本計画に対する受け止めや、使用済燃料対策推進計画の進捗状況について、こちらから説明させていただきました。
それに対し、武藤経済産業大臣からは、日本原燃のしゅん工に向けた支援や、使用済燃料対策の一層の連携強化等によって、業界一丸となって取り組むよう要請がありました。今回、要請いただいた内容は、事業者としても、いずれも極めて重要な、大切な事項だと考えております。
私からは、原子燃料サイクルの早期確立に向けて、再処理工場のしゅん工を、オールジャパンで支えていくことを、改めてお伝えしました。また、使用済燃料対策推進計画の実現など、業界共通の課題について、事業者間で連携・協力を行っていく考えであります。最終処分も含めて、原子燃料サイクル事業の着実な進展に向けて、業界一丸となり、必要な検討や取り組みを進めてまいります。
それでは、テーマに戻りまして、まず、第1点目として、大阪・関西万博について申し上げます。ご案内のとおり、先日4月13日、ついに万博が開幕をいたしました。私自身も出展者の代表として、前日に行われた開会式に参加しました。その開会式では、最先端技術や日本の文化をふんだんに取り入れた華やかな催しで、各国の要人も参加されており、大変、盛り上がりました。今後の万博の成功を感じる素晴らしい会でありました。
そして、翌日の開幕当日は、我々、電事連が出展する「電力館 可能性のタマゴたち」の開館式を行いました。テープカットのイベント後、改めて内部を視察いたしましたが、次世代を担う子供たちが、楽しみながら学ぶことができる、大変すばらしいパビリオンに仕上がっていると思っています。リーフレット類もお配りしていますので、ご覧ください。
電気事業連合会としては、日本で開催された万博に、パビリオンを計4回、これまで出展しております。これまでに、延べ約1920万人の来館者に、それぞれの時代にあわせて、エネルギーの歴史や重要性を伝えてきました。
5回目の出展となる今回のテーマは「エネルギーの可能性で未来を切りひらき、いのち輝く社会の実現へ」です。2050年のカーボンニュートラルの、さらなるその先を見据えて、社会の基盤を支える電力業界ならではの視点で、未来社会を描いていきたいと思っております。
来館者はパビリオンに入るとまず、たくさんの光るタマゴの中から好きなタマゴを一つ選び、首からかけて館内を巡ります。これがそのタマゴ型デバイスでありますけれども、展示や体験と連動して、光ったり、ふるえたりして来館者を誘ってくれます。
メインのエリアでは、未来の社会を支える可能性を持つ約30のエネルギーについて、紹介しています。来館者は、それぞれのエネルギーの特徴や面白さにフォーカスしたゲーム感覚の体験を通じて、未来のエネルギー技術を感じていただくことができます。
例えば、私も参加しましたが、「核融合」の展示では、卓上に、重水素と三重水素の原子核に仕立てた光る球が沢山出てきます。この光る球を、タマゴ型のデバイスに融合させる体験をしていただきます。反発し合う2つの光る球を融合できた時に、エネルギーが生まれます。それで得点が入ります。これは、異なる原子核が融合することで、膨大なエネルギーが発生する「核融合の原理」を体感いただく展示となっております。
また、今回の展示にあたっては、地元の大学生やスタートアップ企業とのコラボレーションにも力を入れてきました。先日、公表しておりますが、海外からのお客さまが、多く来館されることを見据えた多言語サービスもその一つであります。大阪大学の言語サークル「GGC」と、スタートアップ企業でありますPIJINに協力いただきまして、館内の概要を30以上の言語で表現しております。
また、今回の万博には地元の関西電力グループも、水素発電などによるゼロカーボン電力の供給や、陸・海・空のモビリティのプロジェクトに取り組んでおります。その中で、様々な企業と協力し、未来のエネルギーの確立に向けて、チャレンジしております。
様々な技術の未来のつまった万博が、日本で開催されるのは、約20年ぶりとなります。多くの方々に、ご来館いただけることを期待していますし、ぜひ皆さまもご来館ください。
エコキュート出荷台数1,000万台突破
続いて、先週4月11日にお知らせした、エコキュートの出荷台数が1,000万台を突破した件について、申し上げます。こちらは、先週公表したプレスリリースを資料1として配布しておりますので、そちらをご覧ください。
ご案内のとおり、エコキュートはヒートポンプを利用した給湯機で、環境優位性に優れています。2001年に、エコキュートが開発されて以降、電力会社としても普及拡大に努めてきました。加えて、機器メーカーや各種販売店、ハウスメーカー等の方々も、普及拡大にご尽力いただき、このたび1,000万台という大台に到達いたしました。この場をかりまして、関係者の皆さまに、改めて敬意を表します。
本日、取材案内もさせていただいておりますけれども、5月15日には記念式典も予定しています。メディアの皆さまも、ぜひそちらもご取材いただければと思います。
エコキュートにも使用されているヒートポンプは、再生可能エネルギーである大気熱を需要側で利用できる仕組みです。2050年カーボンニュートラルの達成に向けて、暖房や給湯機器などで、さらなる利用が期待できます。先日閣議決定された第7次エネルギー基本計画においても、その重要性が明確化されました。
今回、エコキュートの出荷台数が1,000万台を突破しましたが、仮に1,000万台の全てが、従来のガス燃焼式給湯器から、このエコキュートに置き換わったとして単純計算しますと、年間で、約379万トンのCO2削減効果があるといえます。
加えて、近年、話題となっている太陽光発電設備等の再エネ電源の大幅な増加による出力制御の対策にも活用できます。エコキュートは通常、夜間にお湯を沸き上げますが、例えば、それを太陽光発電の電気が需要を上回る、春や秋などの昼間にシフトすることで昼間の太陽光を有効活用できます。いわゆる「デマンド・レスポンス」としても期待されており、現在メーカーで、技術開発が行われております。
また、ヒートポンプは家庭用のみならず、業務用や産業用での活用も可能です。原子力や再エネの活用といった供給側の脱炭素化と組み合わせることで、さらなるCO2削減効果も期待できるわけです。
資料2として、パワーポイントを配布しておりますので、そちらをご覧ください。ヒートポンプ・蓄熱センターの試算では、足元の2022年度の普及状況は、家庭用の給湯ストック台数で約750万台、業務用給湯約4万6千台となっています。また、産業用加温分野の設備容量で言いますと、約35万kWが導入されています。
2050年のカーボンニュートラルを達成するために必要となる普及拡大が進むシナリオは表の右側になります。家庭用給湯では約5倍、業務用給湯は約20倍、産業用加温分野においては300倍近くの普及が必要となります。
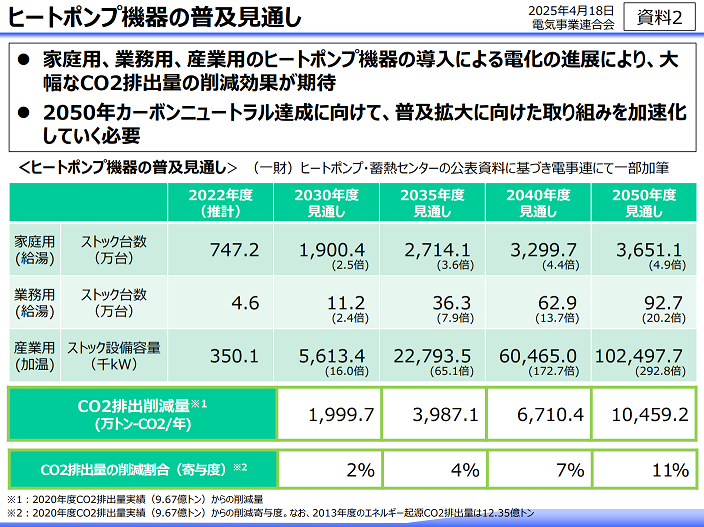
仮に、このような見通しのとおり推移するとすれば、2050年には年間1億トンを超えるCO2の削減効果となります。これは、エネルギーを起源とする2020年のCO2排出量、約9.67億トンの約11%に相当する量になります。
このように再エネである大気熱を活用するヒートポンプは、CO2削減ポテンシャルの非常に高い有効な技術であります。一方で、大気の熱を再エネ熱として活用しているにも関わらず、そのエネルギー利用量は、現在のエネルギー統計に含まれておりません。
欧州では、すでに統計対象としている実態もあります。欧州と同様に統計に含めて、その利用量を適切に把握することは、日本のエネルギー自給率の向上にもつながります。加えて、日本の再エネ量が拡大するため、更なるヒートポンプの利用につながり、カーボンニュートラルの実現を促進する効果もあると思います。国においては、ヒートポンプの普及拡大の支援の拡大とともに、大気熱のエネルギー統計化も検討いただきたいと思っております。事業者としても、引き続き、ヒートポンプ機器の普及促進に努めてまいる所存であります。
本日、私からは以上であります。