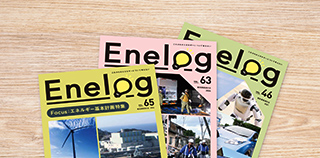昭和後期-2(1970~1988年)
⋯世界の出来事
1970年
-
赤軍派学生による日航機「よど」号乗っ取り事件発生
-
日本万国博覧会開催
-
作家三島由紀夫の割腹自殺事件
-
2月3日
政府、核拡散防止条約に調印を正式決定
-
2月13日
動燃事業団の高速実験炉「常陽」の設置許可
-
3月6日
核拡散防止条約(NPT)、米ソ両国の批准書寄託などにより発効
-
3月14日
日本原子力発電・敦賀発電所が運転開始(初の軽水炉型(BWR)、出力35万7000kW)
-
5月15日
海外ウラン資済開発(株)設立
-
6月12日
IAEAに核拡散防止のための保障措置委員会発足
-
7月15日
東電福島原子力発電所1号炉(BWR、46万kW)臨界
-
7月29日
関電美浜発電所1号炉(PWR、34万kW)臨界
-
12月1日
新型転換炉「ふげん」の設置許可
-
東京電力・横須賀火力発電所8号機が運転開始(合計出力263万kW、当時世界最大)
-
四国電力・坂出ガスタービン発電所が運転開始(初の大容量複合サイクル、出力3万4000kW)
-
硫黄分、ばいじんの出ない燃料LNGを導入した東京電力・南横浜火力発電所が運転を開始。世界初で画期的な取り組みだった
1971年
-
日本マクドナルドの1号店が銀座三越内に開店
-
「仮面ライダー」放送開始
-
日清食品「カップヌードル」発売
-
3月25日
原子力委員会、動力炉開発に関する第2次基本計画を決定
-
4月15日
BWR運転訓練センター設立
-
4月24日
IAEA、核防条約下の保障措置モデル協定で合意に達する
-
8月3日
英、西ドイツ、オランダがウラン濃縮共同計画に基づき、新会社URENCOをロンドンに設立
-
12月16日
原子力季員会、濃縮ウラン確保策として、対米協力、国際濃縮計画への参加、国産化の推進の三本柱で進む方針をきめる
-
東京電力・福島第一原子力発電所1号機運転開始(9電力初のBWR型、出力46万kW)
-
通産省、電気使用制限規則制定
-
環境庁発足
1972年
-
沖縄の本土復帰
-
第11回冬季オリンピック、札幌大会開催
-
連合赤軍あさま山荘事件発生
-
2月21日
日豪原子力協力協定調印(7月28日発効)
-
2月26日
日仏原子力協力協定調印(9月22日発効)
-
3月1日
原研核融合実験装置JFT-2完成
-
4月2日
ENEA改組し、NEA発足(5月9日本参加決定)
-
4月15日
(財)核物質管理センター発足
-
6月1日
原子力委員会、原子力開発利用長期計画を改訂、1985年(昭和60年)に6,000万kWの原子力発電を見込む
原子力発電(PWR)訓練センター設立 -
6月12日
IAEAの枠内で「原子力科学技術に関する研究開発および訓練のための地域協力協定(RCA)」発効
-
8月17日
原子力委員会、ウラン濃縮技術開発に関する基本方針を決定
-
8月29日
じゃがいもの発芽防止に放射線を照射することを、食品衛生法に基づいて厚生省が認可
-
沖縄の返還とともに政府の全額出資で沖縄電力が設立
1973年
-
第1次石油ショック。関西・関東でトイレットペーパーの買いだめ騒ぎ
-
石油ショックを機に省エネの考えが浸透
-
第2次ベビーブーム到来
-
ファクシミリが開発される
-
3月15日
原研JFT-2が高密度、超高温プラズマの閉じこめに成功
-
5月1日
科技庁原子力局に公開資料室を新設
-
7月25日
通産省に資源エネルギー庁を設置
-
8月31日
仏高速増殖炉原型炉フェニックス(FBR、25万kW)臨界
-
10月6日
第4次中東戦争が勃発、世界的な石油供給不安に陥る(第1次石油ショック)
石油代替エネルギーとして原子力のウェイトが高まる -
10月10日
日ソ科学技術協力協定調印、原子力交流を盛り込んだ日ソ共同声明発表
-
12月22日
第4次中東戦争の影響で、政府が石油緊急事態を告示
-
東京電力房総線で初めての50万V送電を開始
-
東京電力の最大電力が2000万kWを突破(8月9日)
-
通商産業省資源エネルギー庁発足
-
中部電力・西名古屋火力発電所、温式排煙脱硫装置運転開始(初の排ガス全量脱硫)
1974年
-
佐藤栄作、ノーベル平和賞受賞
-
巨人軍の長島茂雄(現巨人監督)が現役引退
-
コンビニエンスストア第1号店、セブンイレブンが東京江東区にオープン。朝7時から夜11時までの営業は、当時としては画期的
-
5月1日
日本分析センター設立
-
5月18日
インドが平和利用目的の地下核実験を行ったと発表
カナダ政府、インドへの原子力援助停止を声明 -
6月6日
電源三法(発電用施設周辺地域整備法、電源開発促進税法、電源開発促進対策特別会計法)公布
-
7月16日
日米エネルギー研究開発協力協定調印(即日発効)
-
7月18日
エネ調原子力部会が答申(原子力60年度4,900万kW開発へ)
-
9月1日
原子力船「むつ」出力上昇試験中に放射線もれ、「むつ事件」の発端となる
-
9月3日
第1回世界核医学会議開催
-
10月29日
放射線障害防止中央協議会設立
-
11月15日
国際エネルギー機関(IEA)発足決定
-
第1次石油ショックにともなう電力使用制限の実施。銀座のネオンが消える
-
電力9社がいっせいに電気料金を改定
-
中国電力・島根原子力発電所が運転開始(国産第1号のBWR型、出力46万kW)
1975年
-
子門真人の歌う「およげ!たいやきくん」が大ヒット
-
エポック社より、初のテレビゲーム「テレビテニス」が登場
-
1月29日
米、エネルギー機構を改革。原子力委員会(AEC)を廃し、エネルギー研究開発局(ERDA)および原子力規制委員会(NRC)を発足
-
2月25日
政府、原子力行政のあり方を再検討する原子力行政懇談会(座長:有沢原産会長)を設置
-
4月3日
米NRC、軽水炉の気体放出物による周辺住民の被ばく線量設計目標値を全身で年間最大5ミリレムとする
-
5月3日
核拡散防止条約(NPT)再検討会議開催(ジュネーブ)
-
5月13日
原子力委員会、発電用軽水炉施設周辺の線量目標値をALAPの精神に即して全身で年間5ミリレムと設定
-
7月12日
総合エネルギー調査会需給部会、長期エネルギー計画で原子力発電開発目標を1985年(昭和60年)度4,900万kWとする
-
7月31日
原子力委員会、第二段階核融合研究開発計画決定
-
東京電力・鹿島火力発電所が完成(当時世界最大、合計出力440万kW)
-
関西電力・奥多々良水力発電所が完成(当時日本最大の揚水式、出力121万2000kW)
-
東京電力・袖ケ浦火力発電所2号機が運転開始(国産初のLNG火力、出力100万kW)
-
九州電力・玄海原子力発電所1号機が運転開始(PWR型、出力55万9000kW)
1976年
-
ロッキード事件発生
-
1月3日
原子力先進7か国(米、英、仏、ソ、加、日、西ドイツ)が、核拡散防止の見地から原子力機器輸出規制で合意
-
1月16日
科学技術庁に原子力安全局設置
-
3月1日
原子力工学試験センター設立
-
6月8日
政府、NPT批准
-
7月3日
原子力行政懇談会、「原子力行政体制の強化に関する意見」最終報告を提出
-
9月7日
WHO、放射線照射食品の安全性についての研究結果を発表(ジャガイモ、小麦、鶏肉、パパイヤ、イチゴの安全性を確認)
-
10月8日
原子力委員会、放射性廃棄物対策についての方針を決定
-
10月21日
原子力環境整備センター発足
-
10月22日
自治省、福井県の核燃料税新設を認可
-
11月12日
動燃、独自に開発したウラン一貫製錬装置(PNC法)の全プロセスを完成
-
中部電力・浜岡原子力発電所1号機が運転開始(BWR型、出力54万kW)
1977年
-
巨人の王選手、通算756本塁打の世界記録を樹立
-
この頃からカラオケ・ブーム始まる
-
ピンクレディー「UFO」等の曲が大ヒット
-
2月15日
政府、総合エネルギー対策推進閣僚会議の設置を決定
-
3月21日
米原子力政策グループ、再処理凍結と高速炉の開発延期をカーター大統領に勧告(フォード・マイター報告)
-
3月25日
政府、核燃料特別対策会議を設置
-
4月7日
米カーター大統領、フォード・マイター報告にもとづく新政策を発表
-
4月24日
高速実験炉「常陽」(FBR、熱出力5万kW)が臨界
-
5月7日
ロンドン主要7か国首脳会議開催(INFCEの設置を決定)
-
6月6日
総合エネルギー調査会需給部会、長期エネルギー需給暫定見通しを発表(原子力発電は対策促進ケースで1985年(昭和60年)度3,300万kW、65年度6,000万kW)
-
6月14日
原子力委員会、「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計指針について」および「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針について」を決定
-
9月12日
動燃再処理施設の運転開始で日米共同決定
-
9月22日
動燃再処理工場が運転開始
-
10月1日
米エネルギー省(DOE)発足
-
10月19日
国際核燃料サイクル評価(INFCE)会議設立、ワシントンで総会を開く
-
11月18日
原産、ソ連原子力利用国家委員会と原子力協力協定に調印
-
12月2日
NPT批准を国会で承認、NPT保障措置協定発効
-
東京電力・新信濃周波数変換所が運転開始(電源開発の佐久間周波数変換所と併せて、50ヘルツ、60ヘルツ系統間の2点連係)
1978年
-
植村直巳、犬ぞり単独行で北極点到達
-
成田空港(新東京国際空港)開港
-
1月31日
原子力委員会、環境放射線モニタリングに関する指針を決定
-
3月3日
原子力委員会、長期計画委員会、わが国の原子力発電開発は、軽水炉→高速増殖炉路線であることを確認
-
3月10日
米国の核不拡散法(NNPA)が発効
-
3月20日
動燃新型転換炉「ふげん」(ATR、16.5万kW)臨界
-
4月21日
通産省がカナダ重水炉(CANDU炉)の導入方針をうちだす
-
5月31日
通産省、原発の改良標準化で中間報告
-
6月21日
日独仏高速増殖炉協力協定調印
-
8月25日
わが国「原子力科学技術に関する研究開発および訓練のための地域協力協定(RCA)」に加盟
-
9月12日
原子力委員会、「原子力研究開発利用長期計画」を決定
-
10月4日
原子力委員会を改組、新原子力委員会と原子力安全委員会が発足
-
11月1日
放射線従事者中央登録センターが被ばく線量登録を開始
-
11月28日
日本原子力発電東海第二発電所が営業運転開始、わが国の原子力発電所の設備容量が1,000万kWを突破
-
12月1日
原子力情報センター設立
-
12月6日
電事連、CANDU炉の導入問題に関し、原子力委員会の決定を尊重すると発表
-
電力8社、円高にともなう暫定料金引き下げ措置決定
-
東京電力・福島第一原子力発電所4号機が運転開始(出力78万4000kW、東京電力の発電設備で原子力発電が水力発電を上回る)
-
岩手県葛根田に地熱発電所が運転開始
-
波力発電装置「海明」が実験を始める
-
音声多重放送始まる
1979年
-
インベーダーゲーム流行
-
日本電気、パーソナル・コンピューターを発売。パソコン・ブームの先鞭
-
第2次石油ショック
-
国公立大学、初の共通1次学力試験を実施
-
ソニー、「ウォークマン」を発売
-
東京芝浦電気、初の日本語ワープロを発売。価格は基本構成で630万円
-
1月22日
通産省、原発立地のための公開ヒアリングを制度化
-
1月26日
原子力安全委員会、安全審査のダブルチェック要綱を決める
-
3月28日
米スリーマイルアイランド(TMI)2号機で史上最大の冷却水喪失事故
-
4月16日
スリーマイルアイランド事故にかんがみ、大飯発電所1号機の運転を停止して安全解析を実施
-
5月2日
日米エネルギー研究開発協力協定締結
-
5月19日
原子力安全委員会、大飯発電所1号機の運転再開を承認
-
5月21日
米NRC、3か月間の新規許認可凍結を発表
-
5月28日
原子力安全委員会、米国原発事故調査委、第1次報告書を公表
-
6月11日
第1回日独仏高速炉会議、東京で開催(~6月15日)
-
6月14日
米国務省、使用済み燃料の国際貯蔵施設構想(太平洋ベースン構想)を公表
-
6月26日
通産省、原子力発電所の環境影響調査要綱、審査指針を決定
-
7月12日
中央防災会議、当面の原発防災対策を決定
-
9月12日
動燃のウラン濃縮パイロット・プラント第1期分、1,000台が稼働(12月16日、300kgを初回収)
-
10月1日
日米両政府で東海再処理工場運転期間延長で合意
-
10月23日
米NRC、スリーマイルアイランド事故に関する最終報告書を発表
-
10月30日
スリーマイルアイランド事故について米国大統領特別調査委員会(ケメニー委員会)が、NRCの改組など7項目の勧告をカーター大統領に提出
-
11月19日
原子力安全委員会、低レベル放射性廃棄物の海洋処分の安全性を確認
-
12月7日
米カーター大統領、ケメニー委員会の勧告を支持、新原子力施策を発表
-
12月18日
原子炉等規制法一部改正法施行、再処理民営の途をひらく
-
動力炉核燃料事業団の新型転換炉「ふげん」運転開始(出力16万5000kW)
-
関西電力・大飯発電所1号機が運転開始(PWR型、日本最大の出力117万5000kW)
-
東京電力が世界初のLNG冷熱発電に成功
-
北海道・本州間で電力連携設備が運転開始(連係容量15万kW、初の大容量直流送電方式)
1980年
-
「ルービック・キューブ」がヒット
-
1月17日
原子力安全委員会が初の公開ヒアリングを開催(高浜発電所3、4号機増設で)
-
2月12日
米カーター大統領、放射性廃棄物管理総合政策を発表
-
2月27日
INFCE(国際核燃料サイクル評価)最終総会、平和利用と核不拡散の両立を合意
-
3月1日
民間の再処理事業をめざす日本原燃サービス(株)発足
-
4月1日
産業界の協力受注体制として、高速炉エンジニアリング(株)発足
-
4月8日
ソ連の高速増殖炉BN-600運開
-
4月28日
原子力安全委員会、スリーマイルアイランド事故の教訓から「安全確保対策に反映させるべき事項14項目)を安全審査にとりいれることを決定
-
5月28日
日中科学技術協力協定署名
-
6月3日
原子力安全委員会、原子力防災指針を決定
-
7月21日
原子力委員会食品照射運営会議がタマネギの安全を確認
-
8月14日
南太平洋諸国首脳会議(グアム島)で「安全性が実証されるまで日本の放射性廃棄物海洋処分計画停止を要求する」ことを決定
-
9月18日
理研がトリチウムのレーザー法による分離に世界で初めて成功したと発表
-
10月1日
新エネルギー総合開発機構(NEDO)発足
-
10月23日
原子力工学試験センター安全解析所発足
-
11月2日
電事連、将来濃縮ウランを国産化するとの基本方針を決定
-
11月4日
米大統領にレーガン氏が当選、(直ちに新エネルギー政策の準備はじまる)
-
12月12日
米エネルギー省、放射性廃棄物管理に関する最終環境声明で、地層処分が最善と結論
-
中部電力・奥矢作第一、第二発電所が運転開始(初の2段揚水発電所)
-
九州電力・八丁原地熱発電所が運転開始(日本最大の地熱発電所、出力5万5000kW)
1981年
-
中国残留孤児が初来日し、肉親探し。47人中、26人の身元判明
-
学ランを着たネコ「なめネコ」が流行
-
2月6日
原子力委員会、原子力長期計画見直しを決定
-
3月1日
米レーガン大統領、1982年度原子力予算で米国の高速増殖炉CRBR建設費を認める
-
3月2日
原子力委員会、核物質防護基本方針を決定
-
4月11日
日昇丸、米原潜ジョージワシントン号衝突事故
-
4月18日
原電敦賀発電所で放射能漏洩事故判明
-
5月18日
放射線障害防止法改正法を施行
-
通産省、敦賀発電所事故で報告書、6か月運転停止処分の方針を決定
-
6月7日
イスラエル空軍機、イラクのタムーズ1号研究炉を爆破
-
6月16日
通産省、第2次改良標準化調査報告書を発表
-
7月16日
米レーガン大統領、核不拡散と平和利用協力に関する7項目の声明を発表
-
7月17日
OECD/NEA「放射性廃棄物の海洋投棄に関する多数国間協議監視制度」に正式参加
-
7月30日
第3次改良標準化計画はじまる
-
8月4日
原子力データセンター発足
-
10月2日
原子力安全委員会、初の原子力安全白書をまとめる
-
10月3日
日米両国政府、動燃東海再処理工場の運転を1984年末まで延長ときめる
-
10月8日
米レーガン大統領、原子力開発推進に関して声明を発表
-
11月11日
国連総会、原子力施設への軍事攻撃禁止決議案を採択
-
12月14日
原電敦賀発電所、通産省の特別監察に合格、運転再開へ
-
電源開発・松島火力発電所が完成(石炭専焼では最大の100万kW)
-
東京電力・新高瀬川水力発電所が完成(水力発電としては国内最大、合計出力128万kW)
-
8月に「電気使用安全月間」を設置
-
東京電力の最大電力量が3000万kWを突破
1982年
-
CDプレーヤー、テレホンカード登場
-
エアロビクス流行
-
1月18日
仏FBRスーパーフェニックス砲撃をうける
-
1月22日
原電敦賀発電所1号機運転再開
-
3月5日
日豪両国政府、新日豪原子力協定署名(8月17日発効)
-
3月26日
動燃人形峠ウラン濃縮および製錬転換パイロットプラント全面運転開始
-
3月31日
原研HENDEL本体部完成
-
5月14日
高速増殖原型炉「もんじゅ」建設について閣議了解
-
6月3日
原子力委員会、「原子力開発利用長期計画」を決定
-
6月7日
動燃・日本原燃サービス(株)、技術協力基本協定締結
-
8月27日
原子力委員会、「新型転換炉の実証炉計画の推進について」を決定
-
8月30日
原子力船「むつ」関係5者、新定係港建設および大湊入港に関し正式調印
-
8月31日
原子力船「むつ」佐世保出港(9月6日大湊入港)
-
9月2日
日本、ジュネーブ軍縮委員会で原子力施設への攻撃禁止に関する議定書草案を提出
-
9月3日
動燃高レベル放射性物質研究施設(CPF)においてFBR使用済み燃料の再処理試験を開始
-
9月27日
総合エネルギー調査会原子力部会、通産相に報告書(III)を提出
-
11月22日
高速実験炉「常陽」MK-II炉心初臨界達成
-
11月25日
原子力安全委員会、「公開ヒアリング等の実施方法について」了承
-
12月9日
原研、動力試験炉JPDRの解体届を提出
-
12月29日
国産濃縮ウランを用いた燃料ATRを「ふげん」に初装荷
-
東京電力・福島第二原子力発電所1号機が運転開始(初の国産ユニットでBWR型、出力110万kW)
-
ATR実証炉の建設を主体に電源開発が決まる
-
第1回電源立地促進功労者表彰
1983年
-
中国自動車道、全線開通
-
千葉県浦安の埋め立て地に、東京ディズニーランドが開園
-
日本海中部地震発生。M7.7、死者・行方不明者102人
-
奇病エイズ発生
-
任天堂、「ファミリーコンピューター」発売。ブームが始まる
-
2月23日
動燃・電源開発(株)相互協力基本協定締結
-
5月5日
米核融合炉TFTR完成、試験開始
-
5月27日
高速増殖原型炉「もんじゅ」設置許可
-
12月2日
第1回日中原子力協議(~12月22日、北京)
-
12月23日
原子力委員会、「日本原子力船研究開発事業団の統合について」決定
-
電源開発・竹原火力発電所3号機が運転開始(石炭専焼、単機出力70万kWで国内最大)
-
電気事業用通信衛星「さくら2号」運転開始
1984年
-
NHK衛星テレビ放送開始(本格放送は'87年から)
-
日本人の平均寿命が男女とも世界一に
-
1月1日
中国、IAEAに加盟
-
2月22日
日本原子力船研究開発事業団、関根浜新港建設着工
-
4月1日
ECの核融合臨界プラズマ試験装置JET完成
-
6月21日
IAEA東京事務所開設
-
7月27日
電事連、ウラン濃縮施設、再処理施設、低レベル放射性廃棄物敷地外貯蔵施設について青森六ヶ所村に正式協力要請
-
8月25日
UF6積載仏貨物船「モン・ルイ号」ベルギー沖で衝突沈没
-
9月23日
スイス国民投票で「反原子力二決議案」を否決。原子力政策推進へ
-
11月15日
仏より返還Pu日本に到着、動燃東海事業所に搬入
-
12月1日
ウラン濃縮機器(株)発足
-
電力9社の最大電力が初めて1億kWを超える(8月9日)
-
関西電力・御坊発電所が運転開始(初の人工島方式、出力60万kW)
-
関西電力がデミング賞実施賞を受賞。電気事業では初めて
1985年
-
科学万博つくば'85開幕
-
日本電信電話株式会社(NTT)と日本たばこ産業株式会社が発足
-
日航ジャンボ機墜落事故発生。死者520人
-
関越自動車道、全線開通
-
3月1日
日本原燃産業(株)設立
-
3月31日
日本原子力船研究開発事業団、日本原子力研究所に統合
-
4月5日
動燃東海再処理工場運転再開
-
4月8日
原研JT-60プラズマ初点火に成功
-
4月18日
青森県、六ヶ所村 、日本原燃サービス(株)、日本原燃産業(株)が電事連立合いのもと、「原子燃料サイクル施設の立地への協力に関する基本協定書」を締結
-
5月29日
米NRC、スリーマイルアイランド1号機の運転再開許可
-
5月31日
新型転換炉実証炉建設推進委員会、新型転換炉実証炉建設計画見通し
-
6月5日
米DOE、レーザー濃縮法の採用決定
-
7月23日
米中原子力協力協定調印
-
7月31日
日中原子力協力協定調印
-
9月7日
仏高速増殖炉実証炉「スーパーフェニックス」初臨界達成
-
10月28日
高速増殖原型炉「もんじゅ」工事着工
-
日本の原子力発電設備が2000万kWを突破
-
東京電力・横須賀火力発電所1号機でCOM燃料による運転開始
-
四国電力・伊方発電所2号機、連続運転で日本記録
1986年
-
社会党委員長に土井たか子就任。初の女性党首となる
-
英皇太子夫妻の来日。ダイアナフィーバー起こる
-
3月4日
原子力委員会、「核原料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律」等の一部改正について決定
-
3月31日
「動力炉・核燃料開発事業団の動力炉開発業務に関する基本方針」決定
-
「動力炉・核燃料開発事業団の核燃料開発業務に関する基本計画」決定
-
4月22日
原子力委員会「原子力開発利用長期計画の見直しについて」決定
-
4月26日
ウクライナ(旧ソ連)チェルノブイリ原子力発電所において事故発生
-
6月6日
放射能対策本部放射能安全宣言
-
7月1日
日中原子力協力協定発効
-
7月18日
原子力委員会「放射線利用専門部会」を設置
-
8月14日
ソ連政府、IAEAにチェルノブイリ事故の報告書を提出
-
8月25日
IAEA主催チェルノブイリ事故後評価専門家会合(~8月29日、ウィーン)
-
9月9日
ソ連原子力発電所事故調査特別委員会が第一次報告書をとりまとめる
-
9月24日
IAEA特別総会開幕
-
9月26日
IAEA特別総会早期通報・相互援助条約を採択
-
10月1日
放射線安全技術センターが原子力安全技術センターに改組
-
10月14日
原研JRR-3の撤去作業開始
-
10月27日
原子力事故の早期通報に関する条約発効
-
12月4日
原研JPDRの解体作業に着手
-
「原主油従」時代に。発電電力構成比、原子力26%、石油火力25%
-
東京電力・富津火力発電所1号系列でLNGコンバイドサイクル発電を開始(出力100万kW、88年2号系列出力100万kWも運転開始、合計出力200万kWで世界最大のコンバインドサイクル発電所)
-
電源開発・石川石炭火力発電所が運転開始(沖縄県初の石炭火力、出力15万6000kW)
-
円高と燃料価格の値下がりにともない、2度にわたる電気料金暫定引き下げ
1987年
-
国鉄を分割、民営化し、JRグループを発足
-
1月3日
レーザー濃縮技術研究組合発足
-
2月26日
原子力事故および放射線緊急事態の場合における援助に関する条約発効
-
5月28日
ソ連原子力発電所事故調査特別委員会が原子力安全委員会に報告書提出
-
6月22日
原子力委員会「原子力開発利用長期計画」を決定
-
7月1日
IAEA二条約日本について発効
-
9月11日
原子力委員会「基盤技術推進専門部会」を設置
-
11月14日
新日米原子力協力協定署名(1988年7月17日発効)
-
11月27日
原子力委員会「放射性廃棄物対策専門部会」を設置
-
東京電力の最大電力が4000万kWを突破(8月21日)
-
異常猛暑で首都圏の広域停電が発生
-
国内最大のリン酸型燃料電池発電に成功
-
資源エネルギー庁が毎年5月を「原子力安全月間」と定める
1988年
-
青函トンネル開通。全長53.85km。これにより青函連絡船は廃止
-
瀬戸大橋が開通
-
4月1日
放射能・放射性同位元素の国際単位化、施行開始
-
4月25日
動燃人形峠事業所、ウラン濃縮原型プラント第1期分営業運転開始
-
5月25日
日米新原子力協力協定成立
-
7月17日
日米原子力協力協定発効
-
8月2日
原子力委員会「原子力損害賠償制度専門部会」を設置
-
8月10日
日本原燃産業ウラン濃縮工場事業許可
-
10月14日
日本原燃産業ウラン濃縮工場着工
-
11月16日
青森県原子燃料サイクル推進協議会発足
-
11月27日
核物質の防護に関する条約(P.P.条約)への加入発効
-
12月27日
(財)原子力施設デコミッショニング研究協会発足
-
12月28日
ソ連核融合試験装置「T-15」稼働開始
-
電気料金引き下げ
-
沖縄電力民営化