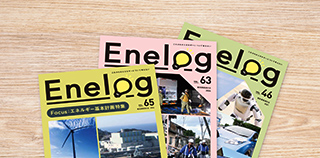明治時代(1868~1911年)
⋯世界の出来事
1868年
-
明治維新。200年以上続いた江戸幕府の崩壊
-
江戸を東京と改称
1870年
-
グラム(ベルギー)が実用的な発電機を開発
1871年
-
廃藩置県
-
洋食店の出現・この頃から洋服の普及が始まる
-
横浜市にガス局が設置され、翌年、ガス灯が点灯される
-
東京-横浜間で電信が始まる
1872年
-
太陽暦の採用
-
戸籍簿の作成が始まる
-
「学問ノススメ」初版。著者は福沢諭吉
-
新橋-横浜間で鉄道が開通
1873年
-
仇討ちが禁止となる
-
野球の初輸入
1875年
-
ロシアと千島・樺太の交換
-
東京(中央)気象台の設置
1876年
-
日曜が休日、土曜が半休(半どん)になる
-
ベル(米)が磁石式の電話機を発明
1877年
-
西郷隆盛ら薩摩士族による西南の役
1878年
-
虎ノ門の工部大学校で、初めて電灯「アーク灯」が点灯。「電気記念日(3月25日)」の由来
1879年
-
エジソン(米)が白熱電灯を実用化。「あかりの日(10月21日)」の由来
1881年
-
ゴーラル(仏)、ギブス(英)が変圧器を発明、交流配電が始まる
-
エジソンによって世界初の電灯事業がニューヨークで開始される
1882年
-
日本銀行創立
-
嘉納治五郎、柔道道場開設する
-
東京・銀座にアーク灯が灯され、市民が初めて電灯を見る
-
世界初の水力発電がニューヨークで始まる
1884年
-
鹿鳴館で仮装舞踏会が盛行。婦人の洋装も盛んに
-
テニスの輸入
-
大阪の劇場でアーク灯が使われる
-
ニコラ・テスラ(米)が提唱した交流方式が電気事業の主力となっていく
1885年
-
日本初の白熱電灯が東京銀行集会所開業式で点灯される
1886年
-
小学校令・中学校令の公布。小学校国定教科書の初めとなる
-
初めての電気事業者として東京電灯会社(現・東京電力の前身)が開業
-
初の自家発電の電灯が大阪の紡績工場で点灯される
-
アメリカで変圧器による交流配電が成功。最初の交流発電所が設立される
1887年
-
名古屋電灯、神戸電灯、京都電灯、大阪電灯が相次いで設立
-
東京電灯が第二電灯局を建設、日本初の火力発電所が誕生(出力25kW)。家庭配電(210V直流)を開始
1888年
-
市制・町村制の公布
-
君が代が国歌とされる
-
東京朝日新聞・大阪毎日新聞創刊
-
初めての自家用水力発電所が宮城紡績所に誕生
1889年
-
大日本帝国憲法発布
-
アメリカから交流発電機を輸入し、大阪電灯が交流式配電を開始
-
東海道本線全通
1890年
-
第1回帝国議会
-
品川電灯開業
-
第3回内国勧業博覧会で日本初の電車運転
-
警視庁が東京電灯に電柱広告を許可(電柱広告のはじまり)
-
深川電灯開業
-
東京-横浜で電話局が開設
-
東京電灯が浅草凌雲閣でエレベーターを運転。初の動力用電力を供給
1891年
-
足尾(渡良瀬川)鉱毒問題起こる
-
西洋住宅が盛んに建てられる
-
帝国電灯開業
-
電気営業取締規則が制定される
1892年
-
東京電灯が電灯1万灯祝典を挙行(開設当時の電灯数130余灯が5年あまりで1万灯を越える)
-
日本初の営業用水力発電所、京都市営蹴上発電所完成(当時の出力160kW、現存する最古の水力発電所で現在も4500kWで稼働中)
-
ドプレー(仏)が水力発電の実用性を証明
1893年
-
前橋電灯設立
-
日光電力開業
-
桐生電灯設立
1894年
-
日清戦争勃発。1895年に下関条約調印
-
石炭の価格の高騰で水力発電企業が続々と誕生
1895年
-
スキーの初輸入
-
八王子電灯設立
-
日本初の市電、京都電気鉄道が開業
-
東京電灯・浅草発電所操業開始。このとき使用したドイツ、AEG製の発電機が50ヘルツであったのが、東日本標準50ヘルツとなる
-
自動車の大量生産始まる。ガソリンの需要増加へ
1896年
-
東京電灯・浅草発電所で国産初の発電機を使用
-
電気事業取締規則が制定される
-
電気事業者の監督行政が全国統一化、この頃の電気事業者は火力発電23カ所、水力発電7カ所、水・火力併用3カ所、電灯数12万余
1897年
-
活動写真興行始まる(大阪)
-
熱海電灯設立
-
大阪電灯がアメリカ、GE製の発電機を増設。この発電機が60ヘルツであったので、西日本標準60ヘルツとなる
1898年
-
最初の政党内閣、隈板内閣成立
1899年
-
猪苗代湖安積疎水を利用した郡山絹糸紡績の沼上水力発電所が運転開始(出力300kW、送電電圧1万1000V、送電距離22.5km、長距離送電のはじまり)
-
甲府電力設立
1900年
-
電灯照明が20万灯に
1901年
-
東京電灯が国産変圧器の使用開始
-
京浜電気鉄道が電灯・電力供給事業を開始
1902年
-
宇都宮電灯設立
-
農業の電化が始まる
1903年
-
日比谷公園公開
-
早慶野球戦始まる
1904年
-
日露戦争勃発。1905年にポーツマス条約調印
-
鉄道の電化が始まる
1905年
-
茨城電気設立
1906年
-
巻煙草ゴールデンバット発売(10本4銭)
-
電灯照明が50万灯に
-
東京電灯・千住火力発電所で初の蒸気タービン発電機の運転開始
-
鬼怒川水力電気、宇治川電気、東京電力など設立される
1907年
-
小学校令改正。6年の義務教育となる
-
東京市の電気局が電灯・電力供給事業を開始
-
電気窃盗事件(1901年)に関連し、窃盗罪について「電気は財物とみなす」と刑法で明文化
-
東京電灯・駒橋水力発電所が一部竣工、東京へ送電開始(初の送電電圧5万5000V、送電距離75km、特別高圧遠距離送電のはじまり)
-
千葉電灯開業
-
電力需要が激増し、電気事業者が増加(電気事業者数146カ所、火力発電7万6000kW、水力発電3万8600kW、電灯数78万2000kW)
1908年
-
常磐電気設立
1909年
-
ハイカラ節の流行
-
逓信省に電気局開設
1910年
-
逓信省に臨時発電水力調査局開設
1911年
-
電気事業法交付
-
猪苗代水力電気設立
-
日本電灯設立(1913年開業、下谷・浅草方面に地中式配電開始)