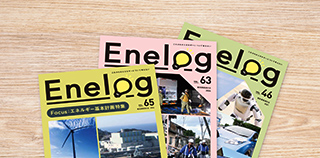対策の強化と貯蔵方法
使用済燃料は、再処理まで安全に貯蔵する必要があることから、使用済燃料貯蔵能力の拡大、貯蔵方法の選択肢の拡充が必要です。
電力各社の使用済燃料貯蔵においては、使用済燃料の発生状況に応じて使用済燃料プールの共用化による号機間移送、リラッキング、乾式キャスクによる発電所構内での乾式貯蔵、中間貯蔵施設の立地など必要な対策をおこなっています。
2015年10月、国のアクションプランにおいて、中間貯蔵施設や乾式貯蔵施設などの建設・活用の促進に向け、電気事業者の積極的な取り組み、事業者間の共同・連携による事業推進の検討の必要性が示されました。
これを受けて、電力9社と日本原子力発電で構成する「使用済燃料対策推進連絡協議会」を電気事業連合会に設置し、使用済燃料貯蔵能力拡大に向けて、事業者全体で「共同での研究開発」「理解活動の強化」「中間貯蔵施設などの建設・活用の促進」等の検討を実施しています。
その後、乾式貯蔵施設については、四国電力が2020年9月に設置変更許可を取得し、2025年7月伊方発電所にて運用を開始しました。
中間貯蔵施設については、東京電力HDと日本原子力発電が設立した、「リサイクル燃料貯蔵株式会社(RFS)」が、2020年11月に使用済燃料貯蔵の事業変更許可を取得し、2024年11月にリサイクル燃料備蓄センターにて事業を開始しました。
関連リンク
使用済燃料貯蔵対策の取組強化について
~使用済燃料対策に関するアクションプラン(骨子)~
-
使用済燃料対策に関する基本的考え方
-
使用済燃料対策の強化へ向けた具体的な取組
-
政府と事業者による協議会の設置
-
事業者に対する「使用済燃料対策推進計画」の策定の要請
-
地域における使用済燃料対策の強化(交付金制度の見直し)
-
使用済燃料対策に係る理解の増進
-
使用済燃料対策に係る理解活動の強化
-
事業者による理解活動の強化
-
核燃料サイクル施策や最終処分施策の理解活動との連携
-
-
六ヶ所再処理工場やむつ中間貯蔵施設など核燃料サイクルに係る取組
-
-
今後の取組(本プランのフォローアップ)
貯蔵方法
使用済燃料の主な貯蔵方法としては、湿式貯蔵と乾式貯蔵の2種類があります。
湿式貯蔵は使用済燃料プールを使って貯蔵する方法です。原子炉から取り出された使用済燃料は、発熱量と放射線量が高いため、使用済燃料プールで水を使って冷却します。そして、水やコンクリートによって放射線を遮へいし、安全に貯蔵管理されます。
乾式貯蔵は、十分に使用済燃料プールで冷却された使用済燃料を、キャスクという容器を使って貯蔵する方法です。キャスクは冷却に水や電気を使わず、空気の自然対流(換気)で冷却することができます。特にキャスクは維持管理の容易さ、施設設置場所の柔軟性、輸送の利便性などにすぐれています。

詳しくは、動画をご覧ください。
使用済燃料の貯蔵方法(湿式と乾式)